キャッシュカード・通帳の不正利用について
盗難にあったキャッシュカードや通帳を不正に利用し、出金する犯罪行為を指します。すり・ひったくり・盗難や暗証番号の盗み見に充分にご注意いただけますよう、お願い申し上げます。
よくある手口
すり・ひったくり・盗難
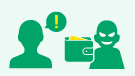
引出し、預入れの際の現金やキャッシュカードを狙ったスリやひったくりなどにご注意ください。二人組の犯行で一人が「お金が落ちている」などと話しかけてお客さまの気をそらせ、もう一人がATMに残っている現金やキャッシュカードを盗んだり、尾行や待ち伏せをするなどの手口で犯行に及んでいます。
暗証番号盗み見
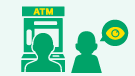
ATMを操作しているときに、後ろからカードの暗証番号を盗み見られ、その後スリやひったくりなどの被害に遭うケースがあります。ATM利用時に後方確認ミラーをチェックするなど周囲の安全にお気を付けください。
お客さまができること
キャッシュカード・通帳の取扱い
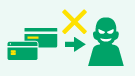
キャッシュカード・通帳は他人に渡さないでください。
警察官や銀行協会事務員を騙る者が、お客さま宅を訪問し、キャッシュカードを騙し取る手口が多発しています。
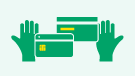
外出時は、キャッシュカード・通帳をお手許から離さないようにしてください。
暗証番号の取扱い
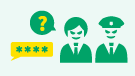
警察官や金融機関等の職員が、暗証番号等を直接照会することはありません。暗証番号は他人に教えないでください。
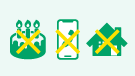
他人に推測されやすい暗証番号は使用しないでください。
(誕生日、電話番号、番地など)
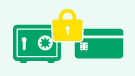
キャッシュカードの暗証番号を貴重品ロッカー等の暗証番号と共用しないでください。
ATMのご利用時について
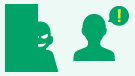
不審者の有無等、周辺の安全に気をお配りください。
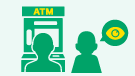
暗証番号等の覗き見にご注意ください。

ATM周辺に見慣れないカード読取機等があった場合にはお気を付けください。
群馬銀行の取組み
暗証番号に関するセキュリティ強化
- ATMによる暗証番号の変更機能
- ATMの通信回線上におけるデータの暗号化実施
- ATMで類推されやすい暗証番号が使用された場合、お客さまに注意喚起メッセージと暗証番号の変更依頼メッセージを画面表示
- 窓口でのキャッシュカード発行時に類推されやすい暗証番号の指定禁止
- ATMで暗証番号を変更する場合、類推されやすい暗証番号への変更禁止
利用限度額に関するセキュリティ強化
キャッシュカードによる1日あたりのご利用限度額などを制限しました。
- 払戻限度額一律設定
- 払戻限度額の窓口での任意設定
- 払戻限度額のATMでの任意設定
- 払戻限度額一律設定の引下げ
- 現金払戻限度額の引下げ
- 払戻限度額の引下げ(個人のお客さま)
その他に関するセキュリティ強化
- ATMへ取引画面覗き見防止シートと後方確認ミラー設置
- ICキャッシュカードの発行
- ICキャッシュカードの発行
- 利便性と安全性を兼ね備えたICキャッシュカードを発行しています。生体認証を必要としない、他行でも利用可能なカードですが、ICチップが埋め込まれた偽造されにくいキャッシュカードです。
- 磁気ストライプ型のキャッシュカードからの切替えをお奨めしております。ICキャッシュカードの発行や、更新にあたっての手数料は無料としております。
- ATMでの異常取引のモニタリング
万が一の場合
キャッシュカードの紛失・盗難等に遇われた場合は、営業時間内はお取引店へ、営業時間外は下記電話番号までご連絡ください。ご連絡いただいた以降は、キャッシュカードが利用されないようにいたします。
なお、下記電話番号は、NTTの電話番号の問合わせ『104』(群馬銀行キャッシュカード紛失・盗難受付係)に登録されております。
お問合わせ
ATM照会センター
偽造・盗難キャッシュカードによる被害者への補償
当行は、偽造・盗難キャッシュカードにより預金を不正に払戻されたお客さまに対し、被害補償を実施しています。
これらの不正な預金払戻被害について、次のすべてに該当する場合に、お客さまは当行に対し被害額の補償を請求できます。
- カードの偽造・盗難に気づいてからすみやかに当行へご通知いただくこと
- 当行の調査に対し、十分な説明を行っていただくこと
- 警察に被害届をご提出いただくこと
お客さまに過失がある場合、補償額は4分の3となります。また、お客さまに重大な過失がある場合、補償の対象となりません。
また、不正な預金の払戻しが、お客さまの配偶者・二親等内の親族・同居の親族・その他の同居人又は家事使用人によって行われた場合、お客さまが被害状況の説明において重要な事項について偽りの説明を行った場合については補償の対象となりません。
 インターネットバンキング
インターネットバンキング ぐんぎんアプリ
ぐんぎんアプリ ぐんぎんビジネスポータル
ぐんぎんビジネスポータル ぐんぎん経営倶楽部
ぐんぎん経営倶楽部 ためる
ためる 運用する
運用する かりる
かりる 便利なサービス
便利なサービス そなえる
そなえる 相談する
相談する 各種お手続き
各種お手続き 資金調達
資金調達 経営・事業サポート
経営・事業サポート 業務効率化
業務効率化